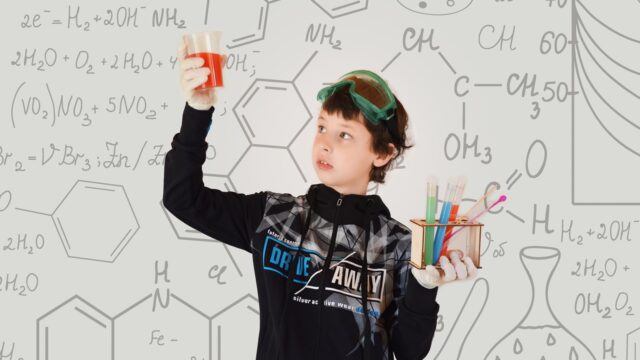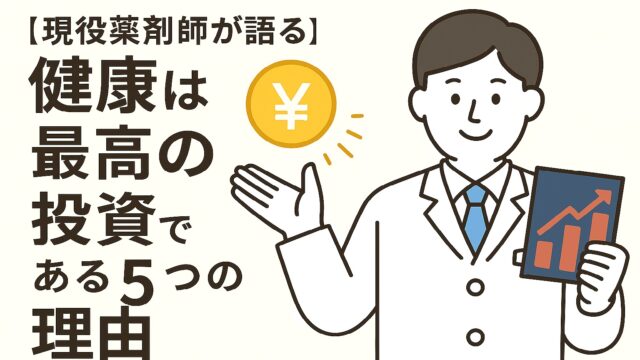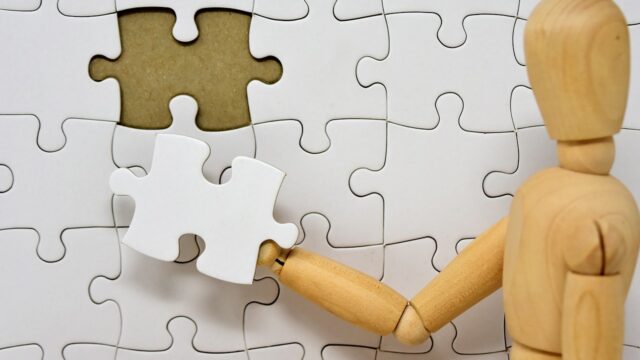「国家資格だから安泰」「高収入で安定」—それが世間一般の薬剤師イメージかもしれません。しかし、現役の病院薬剤師として8年間働いた私が語る現実は、少し違います。
今回は、私が体験した薬剤師になって「よかったこと」(就活の容易さ、安定収入、職域結婚など)と、目を背けてはいけない「悪かったこと」(年功序列、給与に反映されない自己研鑽、病院のブラック労働環境)を赤裸々に公開します。
- 収入とリターンの「コスパ」:私立薬学部で1000万円超の学費と6年間の努力が、なぜ年収アップに繋がりにくいのか?
- 見過ごせない闇: 資格手当が月1,000円という不条理と、蔓延する医療業界の「やりがい搾取」の構造。
- 将来への警告: AIや診療報酬削減の波が、薬剤師の市場価値をどう変えるのか。
これから薬剤師を目指す方、結婚を考えている方へ。この仕事の真の姿を知り、「金」と「時間」に見合ったキャリアなのか、立ち止まって考えてみませんか。
目次
はじめに
これからいろいろと書き連ねていきますが、あくまでも私一個人が思ったことになりますので、薬剤師全員の総意ではないという点はご承知おきください。
また、私自身かなり変わった考えの持ち主なので、変なやつが変なこと言ってるな~くらいのノリで読んでいただけますと幸いです。
病院薬剤師の仕事内容や収入については別の記事で詳しく解説していますので是非そちらもご覧ください!
よかったこと
①就活が楽勝(選ばなければ)

薬剤師は国家資格であり、法律で独占業務が規定されています。
薬剤師の独占業務は調剤業務であり、薬剤師以外の人間が調剤を行うことを法律で禁止しています。(緊急事態においては医師が調剤することは可)
そのため、調剤を必要とする医療機関(病院、薬局、ドラッグストア)には必ず薬剤師を置く必要があり、需要が安定しています。
ドラッグストアなどの薬剤師募集などのチラシでは時給2000円~みたいなのがありますよね。
あれは、薬剤師を設置しないとドラッグストアとしての営業を行うことができず、ただのスーパーになってしまうので、ドラッグストアが薬を売るために絶対に必要な人材(薬剤師)を高時給で募集しているのです。
ある意味法律で守られている領域なので、資格を持っていれば本人に能力があろうがなかろうが一定水準の給与が得られます。
新たにドラッグストアや薬局をオープンする場合には必ず薬剤師の求人が発生しますので、ドラッグストアや薬局が存在し続ける限り仕事がなくなることはありません。
病院や企業などの人気の就職先は倍率が高く、入職試験を勝ち抜く必要がありますが、薬局やドラッグストアであれば余程人間性に問題があるとかでなければ就職は容易です。
就職が容易ということは転職も容易であり、職場が嫌ならやめる人も多いので、薬局薬剤師の転職市場は流動的だと思います。(私の友人も転職者が結構います)
私は2024年度で現職を退職予定であり、次の就職先を探し始めたところですが、募集はたくさんありますので、その中で給与と労働環境(待遇)がいいところを見極めて転職しようと思っています。
②収入が安定している

皆さんご存じの通りですが、薬剤師を始めとする医療従事者の給与は社会保険料から支払われています。
社会保険料はほぼ税金みたいなものですから、売り上げ(病院などの利益)が比較的安定します。
人類が病気にならない・けがをしないという世界にならない限り、医療従事者の仕事がなくなることはありません。
薬剤師はAIに置き換わるなんて数年前から言われていますがそれはまだ先の話です。
薬剤師の業務の一つに医薬品情報を他職種や患者に提供するというのがありますが、確かにこれはAIなどが発達すればなくなるかもしれません。
ググレカスなんてネットで言われるように、ネットが発達した現代であれば大抵の情報は調べれば出てきますし、それをAIに学習させれば質問に対しての解答を導き出してくれるようになるでしょう。(すでにchatGPTにいろいろ教えてもらえますし)
ただし、医学・薬学界隈は常に医学的根拠(エビデンス)と隣り合わせであり、エビデンスは医療の発展とともに日夜変わっていきます。
昔は当たり前だった治療法が現代医学では誤りだったなんてこともあるわけです。
また、現場レベルでは非合理的な判断が必要なケースも多く散見されます。
患者の意向に則した医療は必ずしも医学的に第一優先の治療法ではないケースは往々にしてあります。
それをAIに判断できるのかが医療の今後の方向性を決めると思います。
現場では医師・看護師・薬剤師がディスカッションをして、その患者にあった薬や療法選択を検討しています。
AIの独断と偏見でその3者のディスカッションに勝る日が来れば真っ先に要らなくなるのは薬剤師だと思いますけどね。笑
とはいえ15年から20年くらいあればそれも可能になる気がするので、薬剤師の年収が大幅に下落する日もそう遠くはないと思っています。(悪かったことで詳しくは解説します)
一応、6年制課程を設け、国家試験で数を制限しているので、労働市場への供給過多になることはないと思いますし、国家資格は既得権益で守られているので、薬剤師のAI置き換えはそんな簡単には政府が許さないと思っています。(薬剤師を目指す人が減りすぎても困るからね)
年収は就職先によって結構差がありますが、平均すると500~800万円程度だと思います。
都内であれば平均年収くらいかもしれませんが、地方であれば少し多いくらいの水準かなと思います。
③妻と出会えた

いきなり惚気きた~~~と思われた方。
惚気ではなく大真面目に書いています。
別記事でも何度か書いていますが、私の妻は同じ病院の看護師をしています。
前提ですが、私は元々あまり性欲が強くなく、一人でも特に問題なく過ごせるタイプの人間です。
そのため、大学時代に初めての彼女ができたものの半年ほどで解散し、それからは男友達と遊んだり、ゲームをしたりと楽しく過ごしてきました。
就職してからもそれは変わらず、むしろ仕事に忙殺されてさらに女性への興味も弱くなっていたと思います。
朝8時前に家を出発し、18時頃帰宅。自炊や風呂などのルーチンをこなし、寝るまでのわずかな自由時間はゲームしたりテレビを見て過ごす。そんな毎日でした。
こんななので彼女なんてできるわけもなく、ただただ決まった毎日を過ごしていました。
そんなでしたが、友人たちがどんどん結婚していき遊ぶ頻度が減ってきたことを契機に結婚について考えるようになりました。
なんとなく人生設計として30歳頃には結婚しておきたいな~くらいに思い始めて27歳頃に婚活を開始。
マッチングアプリというのがあるらしいということで「Omiai」というアプリを始めてみました。
マッチングアプリは男性が利用する場合は有料ですが、女性は基本無料です。
男性側はお金を払わないと女性とメッセージのやり取りすらできないので、無課金で利用することはほぼできません。
話が逸れましたが、女性経験が少ない私は6~7人の方と食事に行き、一人女性とお付き合いしました。
ですが、半年ほどで自然消滅しまた彼女がいない日々を過ごしていました。
そんな時に私が担当する病棟の看護師から飲み会に誘われました。
飲み会はあまり好きではありませんが、小規模な飲み会だったので参加してみました。(下心は全くありません)
そこで出会ったのが現在の妻です。
飲み会に誘ってくれた看護師の1学年下で、先輩に可愛がられるタイプだったようで飲み会に来ていました。
5人で飲んでいたと思いますが、テーブル間が少し空いていて、私と妻が対面のテーブル、少し離れたテーブルに他のメンバーが座るという構図になりました。
そこで意気投合し現在に至ります。
馴れ初めは余談でしたが、うちの病院は結構職場結婚している人が多く、知っているだけでも医師と看護師、検査技師と看護師、薬剤師と看護師などいろんな組み合わせのカップルがいます。
そのため、医療従事者と付き合いたい!結婚したいという人にとっては結構いい環境なのかなと思います。
私は独身のころからFIREを目指しており、妻もそれに賛同してくれました。
医療従事者は給与が安定しているので、その点もお互い結婚の決め手の一つだったのかなと思います。
④医師の友人ができた
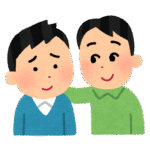
自慢するつもりは全くないですが、一般社会で普通に生活していたら医師と知り合いになるどころか友人になるなんてことはほとんどないですよね?
医師というエリート職の人間がどんなことを考えているのか、普段どんな生活をしているのかいろいろと興味があったのですが、雲の上の存在過ぎて一般ピーポーの私では近づくことすら容易ではないと思っていました。
ですが、彼とは院内のバドミントン部を通じて知り合い、歳が1歳差ということもあって2人で外食やバドミントンをするほどの仲になりました。
いつのまにか私が住んでいたマンションに引っ越して来て、会う頻度はかなり増えましたね(笑)
彼と話をし始めると話題が止まらなくなり、毎回のように気が付けば深夜1時とかになってましたね。
私は人生でここまで話の合う人間に出会ったことがなかったので、医者としてリスペクトしてるのはもちろんのこと、一人の人間として素晴らしい人間だなと思うようになりました。
話している話題はかなり多岐に渡り、時事ネタも多いのですが、主に貯金、投資、世界情勢、医療業界、薬物治療、自己研鑽についてですかね。
たまに会うと、それまでにインプットした知識や気になっていることなどをお互いに聞き合ったり、時にはディスカッションをしたりと無限に話が続きます。
何のめぐりあわせか、彼は研修医を終えてからうちの病院にそのまま残り、まさかの私の担当する病棟の診療科に入局したので、今では同じ病棟で働いています(笑)
⑤転職を気軽に考えられる

これは①の就活がクソ楽とほとんど同じですね。
私は2024年度末で現職を退職する予定ですが、12月末現在で全く就活をしていません。
その最たる理由は遠方に移住するから今就活するのが距離的に難しいというものです。
(移住については別記事を書こうと思っています)
軽く転職サイトを覗いたりするのですが、ぶっちゃけ薬局であれば最悪どこでも働けるので、移住してから探してもすぐ見つかるんですよね(恐らく)。
私のキャリアは大学病院に8年勤務というものしかないですが、就活市場においてはそこそこアドバンテージになると思っています。
いっそのこと保険診療から足を洗って、企業などの開発や薬品管理などもありかな~とか思っていますが、こればっかりは移住先に行ってみないと状況がわからないので、今あんまり活動しても意味ないのかな~なんて思ってます。
職場の同僚には転職先決まったんですか?とよく聞かれますが、本当に全く決まってないですね。
なんなら移住に結構な労力が掛かるので2カ月ほど無職になろうと思っています。
世帯資産が3000万円あるので、無職も全く怖くないというのも心理的に非常にいい影響を与えていると思います。
焦って転職してクソみたいな職場引いちゃったら嫌ですからね(笑)
⑥医学・薬学について幅広く学べる
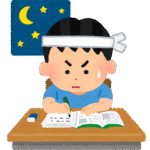
ネットが普及した現代では多くの情報が開かれていますが、それでも医学・歯学・薬学は大学に行かなければ本当の意味で学ぶことができません。
私たちは生物としての生存本能があるので死が怖いと感じるようにプログラムされており、体の調子が悪いとき多くの人は「まさか死なないよね?」って心配になりますよね?
医歯薬学は根幹となる部分は共有知識としてありますが、医師が最も広く深く医学の分野を極めており、歯学・薬学はそれぞれ歯と薬の方に知識が尖っています。
薬学を学べば、体内で起こっていることの多くを理解することができます。
これが理解できないとなぜ薬が効くのか、なぜこの副作用が出るのかなどが理解できないからです。
そのため、自分を始め身内で体調が悪い人がいたら、症状を聞けばある程度状況を理解できます。(診察はできませんが)
市販薬で対応できそうであれば今の症状に適した薬を選ぶこともできますし、無理だから医療機関を受診した方がいいという判断もできます。
身内で薬を飲んでいる人の相談にのることもありますね。(祖父母は見てくれと言わんばかりにおくすり手帳を渡してきます笑)
あと、子供ができてからも薬学を学んでおいてよかったと思いました。
保育園に行き始めてからは月の半分くらいは風邪を引いていましたので、妻がしょっちゅう小児科に連れて行ってくれていたのですが、出された薬が全てわかりますし、ぐずぐずで飲ませられなかった時でも、この薬は今の病態に必須ではないから今回は諦めて次飲める時に飲ませようなどと判断できます。
妻は心配だからか必死に薬を飲ませようとしていましたが、薬剤師の視点で言えば無理に飲ませるほどの薬ではないという判断ができます。
妻も薬剤師が言うならと無理して飲ませようとするのを止め、飲ませ忘れた時でもそこまで自責の念に駆られなくなりました。
小児によく処方される薬剤の小児用量は大体覚えているので、今の体重ならこの量で妥当だなと判断もできるため、安心して薬を飲ませることもできます。
妻や自分が体調不良の時もドラッグストアで成分を確認し、価格を考慮してベストな市販薬を選ぶこともできますので、薬学は家族の健康を維持するという点でも役に立つ知識だと思います。
悪かったこと
①収入が上げにくい(年功序列)
次項の②と被る部分があるので、こちらでまとめて書いておきます。
別の記事でもちょいちょい書いていますが、薬剤師(特に病院)の年収は基本的に年功序列です。
私の病院は典型的な古いタイプの業務体制で、長く勤めている人が優遇され、若者は馬車馬のように働かされるという環境です。
私の病院においては年に1回の定期昇給でしか基本的に給与は上がりません。
昇給幅は徐々に縮小していき15年目くらいからは主査と呼ばれる管理職に昇格するかどうかで給与が変わってきます。
薬剤師のスキルアップには学会や協会が定めている専門・認定薬剤師の資格取得やコ・メディカル共通の認定資格(例えば腎臓病療養指導士など)を取得するという方法があります。
大学院に通って学位(博士号)を取得するという人も少数ですがいます。
認定や専門の資格はその種類によって取得難易度が異なり、難しいものであればその分野の専門医とディスカッションできるレベルの知識を要求されます。
私の病院でも様々な分野の専門・認定薬剤師がいますが、彼ら(彼女ら)は日々医師からの相談を受けて治療の方針などに参画しており、治療に大きく関わっていると言えます。
問題はここからです。
これほどまでに貢献している専門・認定薬剤師ですが、これらの資格を取っても給与はほぼ変わらないのです。
資格取得の難易度に関わらず、病院が定める資格を有している薬剤師は一律月1000円支給されるというのが私の病院の規定なのですが・・・控えめに言って舐めすぎですよね?
資格の取得には時間外に勉強することはもちろんですが、症例を集めて提出したり、学会に所属して学会費を払い、定期的に開催される勉強会に参加(休日)して単位を稼ぎ、ペーパーテストを突破してようやく得られる資格なんです。
それなのに1000円ですよ?ふざけるのも大概にしろって話です。
年間12000円収入が増えますが、税金と社会保険料が取られるので手取りはざっくり9600円。
こんなもん学会費と勉強会への交通費で消えますよ。(交通費は院内規定で10万円まで支給されますが)
勉強会(学会)は全国で開催され、北海道から九州までその年によって開催場所が異なります。
それ故に交通費もバカにならず、多少の自己負担は覚悟しなくてはなりません。
より良い医療を行うために努力して資格を取得し、治療に貢献しているにも関わらず、資格取得をしていない上席のおじさん、おばさんより給料が低いわけです。
薬剤師の知識はある年数まで行くと頭打ちとなり、勉強しない(できない)年配者とゴリゴリに勉強する若手の差は就職5年目くらいで大きな差はない印象です。
特に担当病棟などに配属されると専門性が強化されていくため、若手であってもその分野においては上席者を上回る知識・経験を積むことができます。
それ故に、自分の担当する診療科以外の科が入院してきたときは、その科を担当している薬剤師に教えを乞うことになります。
それは先輩後輩関係ありませんので、私も腎臓関係に関しては先輩や上席者から聞かれることもしばしばです。
つまり、病院薬剤師の能力(知識面)は薬剤師になってからの年数とは比例しないということです。
勉強しなければ新卒4~5年目とさほど変わらないなんてことも往々にしてあります。
そのため、薬剤師(特に病院薬剤師)は市場価値の評価が難しく、認定や専門資格よりも職歴(どんな医療機関で働いてきたか)の方が重要視されるような印象があります。
私も今年度末で現職を退職するため、転職サイトなどで情報収集していますが、年収アップの条件に認定資格などを設定しているところはほぼありません。
ただ、○○資格を持っている方は歓迎!みたいな書き方であり、特別手当が出るとは思えない文言ですね。
また、薬剤師の年収は働く場所によってかなり差がありますが、
一般的には製薬企業>ドラッグストア>薬局>病院の順であり、認定や専門が必要な医療機関は一部の薬局と病院のみです。
この時点で様子がおかしいですよね?
製薬企業は開発、営業(MRなど)で収入は異なりますが、いずれにしてにも年収は高く就職難易度も高いです。
特に開発は国公立の薬学部を卒業したエリートたちや理工学部など化学に特化した大学を卒業した人間が就職するので、普通の私立薬学部卒の人はほとんど就職しないでしょう。
そのため、多くの薬剤師は医療機関に就職することになります。
年功序列でしか収入を上げられず、努力して認定とかをとっても仕事を増やされるだけ。
こんなのやる気がなくなりますよね。
私の職場は就業規則で副業が禁止されているのでアルバイトもできません。
となると、病院薬剤師で収入を上げるには長年勤める以外に方法がありません。
手っ取り早くお金が欲しい人はドラッグストアや派遣薬剤師となって若くから年収600万円とか稼ぐことができますので、稼ぐ方法が無いわけではないです。
稼げる仕事の方がスキルが必要ないという不可解な現象が起こっているのが薬剤師の就職市場の現実です。(医師が美容医療に行くみたいなもんですね)
②スキルや知識を磨いても評価されにくい
ほとんど①で述べているので手短に。
評価されにくいとは金銭的な面とポジション的な面でという意味です。
金銭的な面は上述しましたが、部内におけるポジションも上げられません。
ゴリゴリの年功序列で古い体質のため、若手で知識もあり、スキルがある人であっても無能の40代とかより給料はもちろん安いですし、組織の意思決定に関わることすら許されません。
上司の決めたことは絶対であり、下から文句を言おうとも握りつぶされるというのが現状です。
私も独学でExcelのVBAを学び、業務のIT化を歳の近い先輩方と進めていましたが、上の人たちは記録などを紙ベースでするのが当たり前という考えなのでなかなかスムーズにいかず、一部しか変えられませんでした。
私は特別仕事ができるわけではないですが、得意な部分に関しては上司よりもできると自負しています。
ただ、上司にもメンツと言うものがあり、また上の世代と言うのは大きな変化を嫌う傾向があるので業務改革も骨が折れます。
私に権力があればもっとスムーズだったのかもしれないと思うと悔しい思いとともに虚しさに苛まれました。
結局、職場である程度自分のやりたいように仕事をするには長く勤める以外の方法がないのが非常に不愉快ですね。
博士号を持っている若手(とある先輩)よりもなんの資格もない40~50代の方が給与も権力もあるなんて馬鹿げてます。
業務改革をしようにも上の世代がそれを拒んでくるので、いつまでも無駄な業務が減らないのが現状です。
③労働環境がグレー寄りのブラック
主に病院薬剤師のことですが、院内の薬剤師の労働環境はブラックなところが多いと思います。
私の職場では、日勤は9時ー17時と短めですが、第1.3.5土曜日は半日勤務があり、2連休は月に2回しかありません。
日曜、祝日は基本休みですが、休日出勤も交代制で当てられる場合があります。
そのため、2連休が月に1回とかもざらにあります。
また、若手(30代くらいまで)は月に1~2回当直(夜勤)があるため、2連休が月に1回かつ夜勤1~2回なんて状況が発生します。
土曜半日がある週の日曜日が出勤になるとまさかの13連勤とかになるケースもあります。
有給休暇を使えば回避できますが、チームメンバーの勤務状況や有給の残日数などで使えない場合もあるため、年に1~2回は13連勤になることがあります。
勤務形態については別記事を書いていますのでこちらもご覧ください↓
日勤も定時で帰れることは稀であり、基本30分は残業することになります。
そのため、実態は9時~17時30分と言っても過言ではありません。
施設にもよると思いますが、私の職場は急性期かつ地域の中核病院のため、ほかの病院が断った患者なども基本受け入れるというスタンスです。
そのため、緊急入院(予定外入院)が多く、16時過ぎに緊急入院とかになると残業がほぼ確定するというわけです。
これは医療体制の仕組み上避けられないので、これが嫌なら急性期病院なんて辞めろって話ですね。
医師は原則救急搬送の患者を受け入れなければならず、受け入れれば当然ながらほかのスタッフ(看護師、検査技師、薬剤師など)も対応することになります。
人助けと言えば聞こえはいいですが、これによって自分の心身を病んでしまう医療従事者は後を絶ちません。
病院に就職しようと考えている人はこの現実を理解した上で就職することをおすすめします。
ちなみにゴールデンウィーク、年末年始にも中日(なかび)に出勤がありますし、お盆休みなどは存在しませんのでその点も覚えておいてください。
④将来性が怪しい
これは目を背けてはいけない現実ですが、私はこの先20年以内に薬剤師の給与は大幅に下がると予想しています。
理由はいくつかあります。
1つ目は医療費の増大による診療報酬の削減です。
いろんなところで騒がれているのでご存じだとは思いますが、直近では2025年問題としても取り上げられていますよね。
75歳以上の高齢者が大量に爆誕することによってとてつもない医療費支出が発生することが予想されています。
75歳以上は後期高齢者に該当するため、低収入の高齢者では窓口での医療費負担は1割となります。
つまり、残り9割は社会保険料(税金)で賄うことになります。
高齢者は若者と比較して老化により様々な病気を患うため、医療機関に受診する頻度が高く、回復力も低下しているため治療が長引きコストも多く掛かります。
これは仕方のないことですが、ほとんど医療機関を利用しない現役世代が残り9割を負担するという構図は不公平感があると言わざるを得ません。
昨今のステルス増税や社会保険料増加によって国民負担率はどんどん増加しており、現役世代に払わせるのも近いうちに限界を迎えると思います。
現役世代からお金を取りすぎればそれこそ少子化もさらに加速しますから政府もある程度以上は取れないでしょう。
となると、診療報酬を減らすしかないって話になります。
診療報酬とは医療従事者が医療行為を行った時に発生するお金(技術料)であり、かなり細かく設定されています。
町医者や薬局で算定する診療報酬の種類はさほど多くありませんが、病院(特に急性期病院)では複雑怪奇なほどに種類があります。
診療報酬は厚生労働省が設定しており、行った医療行為に対する報酬になるので、病院の収益や医療従事者の給与に直結します。
診療報酬の大半は医師が算定しており、医師の指示の下、他職種(看護師、作業療法士、管理栄養士など)が医療行為を行った際はそれぞれの職種ごとに算定されます。
薬剤師は独占業務であり、基本的に医師の指示の下で行う医療行為はありません。
そのため、薬剤師の判断で薬剤指導料、抗がん剤調製加算、無菌製剤調製加算などを算定することができます。
まあ種類もそこまで多くなく、点数もそんなに高くないので病院の収益にどれほど貢献しているかは微妙ですが。
話が逸れましたが、基本的な診療報酬は医師ありきで設定されているため、医師が絶対に必要であり、医師がいなければほとんどの算定を取ることができません。
そのため、医師は多くの収入を得ているのです。
それはいいのですが、一連の医療行為を行うのに絶対に必要な職種というのがいまして・・・
個人的に薬剤師はそこに該当しないと思っています。
例えばお腹が痛くなって病院に来たら医師の診察に至るまでに看護師からのアナムネ(情報聴取)、採血があり、診察によってCTが必要と判断されたらCT撮影などが発生します。
ここまでで絶対必要な医療従事者は医師、看護師、臨床検査技師、放射線技師です。
採血やCTで原因が分かったら医師は薬を処方して薬物治療が始まりますが、薬剤師はここで初めて登場します。
薬剤師の仕事内容については別記事で書いているので詳細は省きますが、例えばこの段階で、超高性能のAIを搭載したお薬自販機みたいなのがあったらどうでしょう?
医師の処方意図を正確に理解し、患者の年齢、性別、身長、体重、肝機能、腎機能、既往歴、アレルギー歴など諸々把握して医師の処方が間違ってないと判断できたのなら薬剤師の仕事はなくなります。
人間にしかできない部分もまだありますが、それでも最後だけチェックすればOKみたいなところまではIT技術によって持っていけると思っていて、そうなると高いコストを払って薬剤師を雇用するメリットがなくなるんですよね。
上述したように薬剤師が取れる算定はたかが知れているので、メインの仕事は医師のサポート(薬の相談、ミスのチェック、投与量の計算、相互作用の確認など)と看護師への情報提供とかなので、直接お金が発生するような業務じゃないんですよね。
忙しすぎる医師の業務を一部請け負ったり、医師と看護師の情報の差を埋めたりする地味な役回りなので、医師の負担を軽減したり治療を円滑に遂行させるっていう縁の下の力持ち的な存在だと思っています(病院の場合)。
つまり病院においては絶対に主役にはなり得ない職業なのです。
薬局では一番上に立つ職業ですが、薬局も処方箋ありきの業態であるため、大元である医療機関(医師)がいなければ商売あがったりです。
保険医療に携わる薬剤師は医師がいなければ仕事を取ってくることすらままならないので、今の診療報酬などが改悪されるとなすすべがありません。
仕事のほとんどが受動的な薬剤師は自分で仕事を取ってくるなんてできないので、今の医療システムが崩壊したらそれこそただ薬に詳しいだけの素人社会人です。
技術革新のスピードはすさまじく、私たちの想像超える速さで人間社会に適応できるレベルのAIなどが開発されるでしょう。
そんな時代の変化に対応できる薬剤師がどれほどいるのでしょうか?
私は置いていかれないように別の方法で収入を得る方法を模索しており、最悪薬剤師という職がなくなってもいいように試行錯誤をして備えています。
⑤医療業界の嫌な部分が見えてくる
これは②、③、④を総じて言っているようなものですが、それに加えて、医療の既得権益感というのを常日頃から実感しており、それが嫌な部分だと思っています。
特に、医療における3師(医師、歯科医師、薬剤師)については独占業務と言うものが法律で決められており、この免許を持っていなければできない仕事と言う風に法的に守られています。
3師において医師は取得難易度が非常に高く、取得できればとてつもない権限を手にすることができます。(これが医師の業務量を増やす原因にもなってるんですけどね・・・)
歯科医師、薬剤師は医師ほど取得難易度は高くありませんが、それでも取得までに要する時間や労力は医療職の中ではかなり多いです。(6年制ですし)
加えて、3師を取得するために掛かる学費は国公立であればどの学部でも一律ですが、私立だとべらぼうに高いです。
私立医学部は安いところで6年で2000万円程度で、高いところでは4000万円を超えてきます。
国公立の医学部は本当に限られた秀才しか入学できませんから、医師の大半は私立医学部卒です。
私立医学部に入るには学力ももちろんですが、親の経済力も絶対に必要になります。
2000万~3000万円の学費+6年間の生活費を用意するとなると一般家庭ではほぼ不可能に近く、この時点で医者を目指すというルートが断たれます。
勉強して国公立行けばいいじゃんと思うかもしれませんが、上述したように国公立の医学部は一握りの天才しか入ることができません。
自分の中学の学年1位の人ですら入れるか怪しいレベルです。
そんな狭き門を努力で入ろうとしても非常に厳しく、徒労に終わるのが関の山でしょう。
つまり、この時点でかなり格差が生じているのです。
中流階級の家庭に生まれて、偏差値が65程度あったとしても医者にはなれないですが、親が医者や高年収職であれば努力次第で目指せるスタートラインに立つことが許されます。
医学部に入ってからも膨大な時間勉強して国家試験をパスした医師たちは自信に満ちており、時には若手であってもおらついたりするケースが少なくありません。
そりゃ、ストレートであれば25歳とかの若造が製薬メーカーの営業のおじさんから先生先生なんて言われてたら天狗になるのも当然です。
研修医の頃は腰が低かった医師も4~5年目くらいからおらつく人がちらほらいます。
権力を持つと人は変わるというのを目の当たりにしているような感じがしてすごく嫌ですね。
私も今年で32歳になりましたが、年下の医師にため口とかで対応されると正直イラっとします。(俺はお前の友達じゃねえぞって言いたくなりますね)
昔よりは減ったそうですが、いまだに看護師に怒鳴る医師もいます。
常に緊張感をもってストレスフルに働いているので気が張り詰めることはだれしもあるとは思いますが、仕事でそれを出すのはスマートではありませんよね。
結局、医師からしたら自分が主役でほかは脇役くらいなもんで、間違いを指摘すると不機嫌になる人もいます。
責任や労働力の対価として多くの報酬を貰っているというのは頭ではわかっているのですが、ほかの職種との差が激しすぎて、やっぱり一緒に医療をしているという気になれません。
もちろん本人が努力して今の地位にいるのはわかっているのですが、既得権益を使って院内で偉そうにしたり金を稼いでいるという一面があるのは紛れもない事実だと思います。
そういった院内のカースト的なものは大きな病院であればあるほど色濃いと思っています。
小さな病院であれば、医師、看護師、薬剤師などの距離感が近く、風通しもよさそうですが、大学病院なんかは科長とかになると教授とかの称号があるので、ミスを指摘するのもびくびくします。
自分が偉いとか薬剤師だってすごいんだなんてこれっぽっちも思っていませんが、これだけ格差があるのは正直精神的に辛い部分がありますし、薬剤師的にはこっちの方がいいと思っても気軽に提案しにくい環境というのは仕事のやりづらさにも繋がりますね。(場所によるんでしょうけど)
これから薬剤師を目指すことをおすすめするか
私がもし高校入試くらいまで戻れるのなら、薬剤師を目指すかと言われたら・・・
目指しません!!
理由はあくまでも私の考えですが、薬剤師になるための勉強時間やコスト(学費)とリターン(収入、労働環境)が見合っていないと思うからです。
加えて、上述したように、薬剤師になってからの自己研鑽は本当に自己満足の世界であり、勉強しても収入は上がらないが勉強しなくても下がらないという摩訶不思議な世界なので、勉強しようという意思が無くなります。
勉強時間や学費とリターンが合っていない点についてですが、国公立の薬学部を卒業した場合はその限りではありません。
ですが、一般的に国公立の薬学部に行けるほどの頭脳の持ち主は普通の薬剤師にはならない(研究・開発方面に行く)場合が多いので、基本私立薬学部の話だと思ってください。
私立薬学部の6年間の学費は大学にもよりますが概ね1200万~1500万円ほど。
加えて入学金、教科書代が掛かりますし、一人暮らしをしている人は生活費も加わりさらに多くの費用が掛かります。
普通の大学生くらい遊べるのは1年生の時だけで、それ以降は必修講義と実験がぎっちり詰め込まれ、4年から5年への進級時にはCBTとOSCEという仮免試験を受けなければなりません。
一定数単位を落とせば留年確定という世界で6年間過ごし、6年生の9月以降は食事睡眠以外はほぼ勉強するという生活を過ごしてようやく国家試験にたどり着きます。
国家試験の合格率はその年ごとに異なりますが、概ね65~75%程度です。
そうしてようやく薬剤師になって稼げる年収が平均500~700万円です。
冷静にコスパ悪くないですか?
今だからこう思えますけど、薬剤師になるために費やした時間を別のことに注げたのならもっと年収の高い仕事ができていたんじゃないかなと思ってしまいます。
メーカーの開発職などは国公立出身の優秀な一握りの人材しか就くことはできませんし、高年収を望むのなら製薬会社のMR(医療情報担当者)などの営業職に就くしかありません。
その他多くの薬剤師の勤め先である病院、薬局、ドラッグストアでは長く勤めなければ800万円などの年収を得ることはできません。
病院や薬局に就職すると、毎月のように発売される新薬の勉強を欠かすことはできず、さらなる高みを目指す人は専門や認定資格の取得を目論見ます。
何度も言うようですが、薬剤師の専門や認定資格は取得難易度と得られるリターンが全く釣り合っていません。
得られるのは己の満足感(達成感)とバカにしているのかと思えるほどのお手当だけです。
やりがい搾取が蔓延る医療業界の闇そのものであり、まともに付き合っていたらプライベート時間なんて作れません。
私は多くの考え方に触れた結果、やっぱり頑張った人は報われるべきであり、対価と言うのは資本主義の現代においては「金」以外はあり得ないという考えに至りました。
金が稼げないことに時間を使うのは趣味・娯楽であり、自己研鑽とは異なると考えます。
以上から、薬剤師になってからも勉強は続くのに、収入の増え幅は乏しく、努力量に比例しない現状を考慮すると薬剤師を目指すことはおすすめしません。
まとめ
今回は(病院)薬剤師になってよかったこと、悪かったことと題して長々と書き連ねてきました。
現在薬剤師として活躍されている方を否定するつもりは全くないですが、医療界隈でも日の目を浴びにくい職業ですし、患者さんからも感謝されにくいポジションだと思います。
テレビドラマとかでも露骨ですが、医者=神様みたいな描かれ方をされており、それ以外は治療において脇役感が否めません。
目立ちたいとか崇め奉って欲しいとかそんなことは全く思っていませんが、やっぱり薬剤師の仕事って地味ですし、私はやりがいをあまり感じません。
あんなに薬学が好きだったのに、今は業務をこなすことばかりに気を取られて本当にやりたかったことってなんだろうと常々思っています。
金を稼ぐと割り切れればいいのかもしれませんが、上述したように将来性は怪しく、このままレールの上に乗っていれば一生安泰なんてことはないので、やっぱりほかのスキルを習得することに時間を投下した方が合理的だと考えます。
AIなどの技術革新の波はもうすぐそこまできています。
時間もお金も限られていますから、本当に自分がやりたいこと・就きたい仕事につくための努力に時間とお金を投下してみることをおすすめします。
以上、参考になれば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。